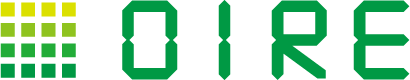第6期修了生の声
Alumni Testimonials
清水 友子
IRとの出会いと学び合い
IRプログラムは、「IR」に初めて出会い学び始める方にとっても、これから広く扉が開かれていくと予見しています。私自身も、IR担当者の業務に必要な知識・スキルを習得しました。
私が所属する大学生協は、大学の教育・研究の発展に協力する使命を掲げています。その中の担当店舗では、学生の学修や進路選択に関する実態調査も実施し、時には大学へデータ報告も行います。本プログラム受講前、新たな調査を担当した私は、無力感をおぼえていました。データ処理を試みてExcelの数式を入れるも作業量が膨大で、肝心の分析・考察には一向にたどり着けません。袋小路に入る中、ある催事で本プログラム主担当の藤原宏司教授のデータ報告を聴きます。整然とした内容が心に残り、分析業務のヒントを得たいと先生を訪ね、このプログラムと出会いました。
特に学びを深めたプログラム内容の1つに、「探索的データ分析(EDA)」があります。架空の大学職員の在職状況に関するデータセットを用いて、様々な視点でデータを集計・可視化し、データの特徴を理解するプロセスを体得します。
この集計過程で、習得したRのコード活用等により、受講前よりずいぶんとデータ処理速度が向上していることに気づきました。
また、データ分析の視点も少しずつ養われています。分析方針を定める上では「何の目的で扱うデータか」を考え続けることが重要です。扱ったデータセットの例では、「退職した職員が、なぜ辞めたのか」という問いの裏側には、「在籍する職員が、なぜ働き続けているのか」という問いも存在します。裏表の問いですが、どちらの視点に立って分析するかで提供する情報は大きく異なります。ここで、もし自分がこの大学で職員教育を担当する立場だとすると、どう考えるでしょう。在籍する職員に関心を向けて、働き続けられる職場を作りたいと考え、それに伴って報告すべきデータも取捨選択できるようになります。
データを見る視点を本質的に理解し始めたのは、最終回のプレゼン発表会のフィードバック後と言えます。半年間データ探索をした今もなお、分析業務の奥深さ・難しさ・面白さをより一層かみしめています。
※ ここで触れたデータセットの事例は第6期の学修内容です。最新のカリキュラムは募集要項や講義資料等を参照ください。
プログラム全体にわたり、同期受講生の皆さんと協同(協働)して学び合った成果も、大変価値があります。各大学の事例や課題意識、データ分析の視点は示唆に富み、自分の業務への応用を考えられました。このプログラムや現場業務での皆さんの頑張りにどれほど勇気づけられてきたかは、言葉に尽くし難いものです。
自分を成長させてくれる方々との出会いは、いつ訪れるか分かりません。全国の受講生・先生方と繋がるこのプログラムでは、その好機に恵まれる可能性も広がります。
私の今後の目標は、学修成果をもとにデータマネジメントの仕組みを作り、一歩ずつ広げていくことです。同時に、職員一人ひとりがデータ分析を進める視点を養い、レポーティングをするスキルも求められます。まずは、職員会議にて今後予定するプログラムの成果報告を皮切りに、組織に貢献したいと思います。
「IR」が持つ役割を見つめて、このプログラムでの学修は、大学経営に限らず「組織の意思決定をサポートするための、効果的な情報提供」に広く活きると私なりに意義付けています。これから受講する皆さんも、受講目的を設定し、プログラムを楽しまれることを願っています。